
惗棟妛偲儊僇僯僘儉
乥 傾僾儘乕僠(1) 乥 傾僾儘乕僠(2) 乥 傾僾儘乕僠(3) 乥 傾僾儘乕僠(4) 乥 傾僾儘乕僠(5) 乥
愛怘丒殝壓忈奞傊偺傾僾儘乕僠乮3乯
偙傟傑偱殝壓偺儊僇僯僘儉偵偮偄偰惗棟妛揑娤揰偐傜2夞偵傢偨偭偰峫嶡傪峴側偭偰偒偨偑丄崱夞偼殝壓婡擻偺昡壙偺曽朄偵偮偄偰弎傋偰傒偨偄丅
摿梴儂乕儉偺殝壓忈奞偺幚懺
傑偢昡壙偵愭棫偪丄摉堾偺朘栤愭偱偁傞摿暿梴岇榁恖儂乕儉偵偍偗傞殝壓忈奞偺幚懺挷嵏偐傜丄梫夘岇崅楊幰偵偍偗傞殝壓忈奞偺徢忬偲敪尰昿搙偺娭學傪丄Sonies BC et al丂1)偵傛傞殝壓栤恌昞傪梡偄偰挷嵏乮枹敪昞乯傪峴側偭偨偺偱丄偦偺寢壥傪帵偟側偑傜姵幰偺娤嶡偵嵺偟偰拲堄偡傋偒億僀儞僩偵偮偄偰弎傋偰傒偨偄丅
| 丒棳煹 | 22% |
| 丒怘傋傞偺偑抶偄 | 22% |
| 丒堸傒崬傒偑崲擄 | 20% |
| 丒堸傒崬傓帪偵儉僙傗奝偑弌傞 | 20% |
| 丒怘傋暔偑愩偺墱傗岮偵堷偭偐偐傞 | 14% |
| 丒岮偵媗傑偭偨姶偠偑偡傞 | 12% |
| 丒岥偐傜怘傋暔偑偙傏傟傞 | 10% |
| 丒屌宍暔偺曽偑悈暘傛傝堸傒崬傒偵偔偄 | 10% |
| 丒悈暘偺曽偑屌宍暔傛傝堸傒崬傒偵偔偄 | 10% |
| 丒堸傒崬傓慜偵儉僙偨傝奝崬傫偩傝偡傞 | 4% |
| 丒偟偽偟偽攛墛傗婥娗巟墛傪孞傝曉偡 | 4% |
| 丒岥偺拞偵怘傋暔偑巆傞乮帟偲杍偺娫乯 | 4% |
| 丒憠偣偨 | 2% |
殝壓忈奞姵幰偺敪尒偺巺岥偵側傞偦偺挜岓偼偳偺傛偆側傕偺偐偲偄偆偲丄昞侾偵嫇偘偨徢忬偲偦偺敪尰昿搙偑殝壓忈奞姵幰偺慽偊偱傕偁傞偺偱丄拲堄偟偰娤嶡偟偨偄丅栤恌昜偺崁栚偺丄1.堸傒崬傒偑崲擄丄2.堸傒崬傓帪偺捝傒丄3.儉僙傞丄4.奝偒崬傓側偳偵壛偊偰丄旲偐傜偺媡棳偺妋擣傕廳梫偱偁傞丅偝傜偵丄岆殝惈攛墛丒拏懅丒扙悈側偳偺婛墲楌偺忣曬傪妋擣偡傞偙偲丄傑偨偦傟傜偺忣曬偲偲傕偵丄悈暘偲屌宍暔偺偳偪傜偺宍忬偑殝壓偟傗偡偄偐偺妋擣偼丄娪暿恌抐偲偟偰桳岠偱偁傞丅偝傜偵怘暔宍懺丄怘帠偺強梫帪娫丄怘帠夞悢丄愛庢検偲偄偭偨揰偵偮偄偰傕忣曬傪妋擣偟偰偍偔偙偲傪朰傟偰偼側傜側偄丅
| 丒偒偞傒怘 | 68% |
| 丒儈僉僒乕怘 | 16% |
| 丒晛捠怘 | 12% |
| 丒宱旲揑宱娗塰梴乮NG朄乯 | 2% |
| 丒拞怱惷柆塰梴乮IVH乯 | 0% |
| 丒偦偺懠 | 2% |
昞2偵摿梴儂乕儉偺怘帠宍懺偺幚忬傪婰偟偨偑丄"偒偞傒怘"偱偺懳墳偑旕忢偵懡偔丄堦斒揑偵嵶偐偔崗傓偲怘傋傗偡偄偲偄偆岆偭偨曔傜偊曽偑尰応偵嫮偔尒傜傟傞偺偑傛偔傢偐傞丅愩偺杻醿摍偺偨傔怘夠宍惉擻偺掅壓偟偨働乕僗傗丄憲傝崬傒忈奞偑偁傞応崌丄"偒偞傒怘"偼偐偊偭偰岆殝偺尨場偲傕側傝丄挷棟偺宍懺傕婡擻偵崌傢偣偨撪梕偲偡傞偙偲偑戝愗偱偁傞偑丄塰梴怑堳偲偺嵶偐側僐儈儏僯働乕僔儑儞偑廳梫偱偁傞丅
殝壓忈奞偺昡壙
扨偵殝壓忈奞偺傒側傜偢儕僴價儕僥乕僔儑儞堛椕偺椞堟偱偼丄婡擻忈奞傗擻椡忈奞偺桳柍傗掱搙偵偮偄偰"偦偺忈奞傪偳偺傛偆偵昡壙偡傞偐"偑旕忢偵廳梫偱偁傞丅傑偨儕僴價儕僥乕僔儑儞傪幚嵺偵恑傔偰偄偔忋偱偼僑乕儖乮栚昗乯偺愝掕偑嬌傔偰戝愗偵側傞偑丄姵幰偺孭楙偺僾儘僌儔儉傪棫偰偰偄偔嵺偵傕媞娤揑側昡壙側偔偟偰偼孭楙寁夋偺棫埬傕弌棃側偄丅
偝偰丄儕僴價儕僥乕僔儑儞堛妛偵偍偗傞昡壙偺曽朄偵偮偄偰偼庡偩偭偨傕偺偱偼丄擻椡掅壓偵娭偡傞昡壙朄偲偟偰丄ADL Index 丄Barthel
Index偑偁傝丄嵟嬤偱偼婡擻揑帺棫搙昡壙朄 (FIM:Functional Independence Measure)丂俀)偑棙梡偝傟偰偄傞偑丄殝壓婡擻傪昡壙偡傞曽朄偲偟偰偼尦棃尵岅婡擻偺昡壙曽朄傪弨梡偟偰偄傞偺偑幚忬偱偁傞丅偲偙傠偱僗僺乕僠丒儕僴價儕僥乕僔儑儞偵偍偄偰傢偑崙偱堦斒揑偵墳梡偝傟偰偄傞昗弨幐岅徢専嵏側偳偼丄尵岅忈奞偵偍偗傞敪榖儊僇僯僘儉慡懱偺婡擻傪掕検揑偵昡壙偡傞偙偲偑側偐偭偨偨傔偵彅奜崙偵抶傟偰偄傞偲偄傢傟偰偒偨偑丂3)丄偙偆偟偨栤戣偵懳墳偡傞昡壙朄偲偟偰乽埉幃敪榖儊僇僯僘儉専嵏乿偑奐敪偝傟棙梡偑恑傫偱偄傞丅摉堾偱偼偙偺乽敪榖儊僇僯僘儉専嵏乿傪娙棯壔偟偰殝壓忈奞姵幰偺昡壙朄
乮昞3乯偲偟偰偄傞偺偱徯夘偟偨偄丅
| 戝崁栚 | 彫崁栚 | 侽 | 侾 | 俀 | 俁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘥.屇媧婡擻 | 侾 | 屇媧悢乛侾暘 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俀 | 嵟挿屇婥帩懕帪娫 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俁 | 儘乕僜僋徚偟 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 嘦.敪惡婡擻 | 係 | 嵟挿敪惡帩懕帪娫 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 嘨.旲堲岮暵嵔婡擻 | 俆 | 乛a乛敪惡帪偺帇恌 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俇 | 岥奧斀幩 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俈 | Blowing帪偺旲楻弌 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 嘩.峔壒塣摦婡擻 | 俉 | 岥怬偺埨惷帪 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂丂a.埨惷帪偺忬懺 | 俋 | 愩偺埨惷帪 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 侾侽 | 壓妠偺埨惷帪 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 侾侾 | 帟偺忬懺 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 侾俀 | 欩崌忬懺 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 侾俁 | 媊帟揔崌忬懺 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂丂b.塣摦斖埻 | 侾係 | 忋怬傪側傔傞 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 侾俆 | 壓怬傪側傔傞 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 侾俇 | 愩偺塃堏摦 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 侾俈 | 愩偺嵍堏摦 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 侾俉 | 愩愲偺嫇忋 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 侾俋 | 峝岥奧傪側傔傞 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俀侽 | 塃偺杍傪墴偡 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俀侾 | 嵍偺杍傪墴偡 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俀俀 | 杍傪傆偔傜傑偣傞 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俀俁 | 岥怬偺暵嵔 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俀係 | 岥怬傪堷偔 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俀俆 | 岥怬偺撍弌 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂丂c.斀暅塣摦偱偺懍搙 | 俀俇 | 愩偺撍弌亅屻戅 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俀俈 | 愩偺嵍塃堏摦 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俀俉 | 楢懕愩懪偪 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俀俋 | 岥怬偺奐暵 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俁侽 | 壓妠偺嫇忋亅壓惂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 嘪.愛怘婡擻 | 俁侾 | 棳煹 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俁俀 | 庢傝崬傒 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俁俁 | 欚殣 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俁係 | 殝壓 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 丂 | 俁俆 | 僗僩儘乕偱媧偆 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
敪榖偼変乆偑僐儈儏僯働乕僔儓儞偺昞弌庤抜偲偟偰嵟傕傛偔巊偆傕偺偱偁傞丅椺偊偽傢傟傢傟偑乽傝傫偛乿偲偄偆扨岅傪壒惡昞弌偡傞偨傔偵偼傑偢摢偺拞偱乽傝傫偛乿偺堄枴奣擮傪憐婲偡傞丅偦偟偰偦偺堄枴奣擮偵懳墳偡傞壒宍傪傂偭傁傝偩偟偰偔傞丅擔杮岅側傜傝傫偛丄塸岅側傜倎倫倫倢倕偲側傞丅偙偺抜奒傪尵岅妛揑抜奒偲偄偆丅偦偟偰偦傟偧傟偺壒傪敪惡敪岅婍姱傪摦偐偡偙偲偵傛偭偰幚尰偟偰偄偔偙偲偵側傞丅偙偺抜奒傪惗棟妛揑抜奒偲偄偆丅敪榖偺忈奞偵偼(1)傠傟偮偑傑傢傜側偄丄(2)堘偆岅壒偑偱傞丄(3)偼側偟偑偼偭偒傝偟側偄丄(4)旲惡偑傂偳偄丅(5)惡偑偪偄偝偄丄(6)榖偟曽偑偼傗偡偓傞丄(7)惡偑偍偐偟偄側偳偺徢忬偑傒傜傟傞丅擔忢偱偼惡偲偙偲偽偼摨媊偲偟偰巊傢傟偙偲傕懡偄偑丄偙偙偱偼惡偲偼惡幙偺偙偲偱偐偡傟偨傝偑傜偑傜偟偰偄偨傝偡傞偺偑惡偺堎忢偱偁傞丅偙偲偽偲偼幚嵺偵榖偝傟傞擔杮岅偺偙偲偱偁傞丅敪榖偼惡傕偙偲偽傕娷傔偨傕偺偵側傞丅
敪榖忈奞偼尵岅妛抜奒偱傕惗棟妛揑抜奒偱偳偪傜偱傕偍偙傞偺偱娪暿偑昁梫偱偁傞丅偦偺偨傔偺堦偮曽朄偲偟偰敪惡敪岅婍姱偺専嵏偑桳岠偱偁傞丅傕偟専嵏忋栤戣側偗傟偽尵岅妛揑抜奒偺忈奞偱偁傞丅惉恖側傜偽幐岅徢側偳偑峫偊傜傟傞丅専嵏忋栤戣偑偁傟偽惗棟妛揑抜奒偺忈奞偱専嵏偺寢壥偑敪惡敪岅婍姱偺偳偙偵栤戣偑偁偭偰偍偙傞偺偐尨場媶柧偺偨傔偺忣曬偺傂偲偮偵側傞丅敪惡敪岅婍姱偲偼戝偒偔傢偗傞偲敪榖偺僄僱儖僊乕尮偲側傞屇媧婍丄屇媧婍偐傜偺屇婥棳傪惡偵偐偊傞岮摢丄岅壒偺惗惉傪偍偙側偆愩丒岥怬丒壓妠丒帟夊丒旲堲岮側偳偱偁傞丅偙傟傜偺婍姱偺宍懺媦傃婡擻偵栤戣偑偁傞偐偳偆偐偺僠僃僢僋昞偑昞3偱偁傞丅
俙俽俵俿乮埉幃敪榖儊僇僯僘儉専嵏乯係乯偼埉拞墰昦堾偺惣旜巵偺奐敪偝傟偨傕偺偱慡懱偼6偮偺戝崁栚丄俇俋偺彫崁栚偐傜側傞専嵏朄偱偁傞偑丄摉堾偱偼偦偺撪俁俆偺崁栚偵峣偭偰殝壓婡擻偺僠僃僢僋傪峴側偭偰偄傞丅偦偺偆偪偺廳梫側崁栚偵偮偄偰娙扨偵夝愢偟偰偍偒偨偄丅
傑偢屇媧婡擻偱偼屇婥偺帩懕帪娫傪應掕偡傞丅偙傟偼嵟戝媧婥屻丄偱偒傞偩偗挿偔偦偭偲僼偺壒偺峔偊偱懅傪偩偟偰偄偔丅屇媧婡擻偵栤戣偑偁傞応崌偼敪榖偑彫偝偔偰暦偒庢傝偵偔側偭偨傝晄帺慠側偲偙傠偱愗傟偨傝偡傞丅岮摢偺婡擻偱偼敪惡帩懕帪娫傪應掕偡傞丅偙傟偼挿偔傾乕偲偄傢偣偰應掕偡傞偑屇婥帩懕帪娫傛傝抁偗傟偽岮摢偵側傫傜偐偺栤戣偑偁傞偲峫偊傜傟傞丅丂師偵擃岥奧偺埨惷帪偺忬懺傪帇恌偡傞丅埨惷帪偵偼寬懁岥奧媩偑壓悅偟傑偡丅師偵傾乕偲敪惡偝偣側偑傜擃岥奧偑嫇忋偡傞偐偳偆偐傪傒傞丅幨恀侾偺傛偆偵嵍塃偳偪傜偐偵乮岥奧悅偑寬懁偵乯曃埵偟偰偄傞偙偲傕偁傞丅傾乕偺敪惡帪偵偒偪傫偲擃岥奧偑嫇忋偟偰旲堲岮暵嵔偑偍偙側傢傟偰偄傞偐偳偆偐偼旲岴偵彫巜傪偐偞偟妋擣偡傞偙偲傕偱偒傞丅旲堲岮暵嵔晄慡偑偁傟偽敪榖偼奐旲惡偲側傝僼僈僼僈偟偨傢偐傝偵偔傕偺偵側傞丅偙偙偱拲堄偟側偗傟偽側傜側偄偺偼旲岴偐傜屇婥偑傕傟偨傝擃岥奧偺嫇忋偑傛偔側偔偰傕奐旲惡傪偟傔偝側偄恖傕偄傞偺偱偁偔傑偱傕敪榖偵栤戣偑側偗傟偽偐傑傢側偄偲偡傞偙偲偱偁傞丅偝傜偵旲堲岮暵嵔婡擻偱偼丄岥奧斀幩傪傒傞丅擃岥奧偺椉懁傪岥奧媩偵増偭偰柸朹偱偙偡傝擃岥奧偺嫇忋偺掱搙傪帇恌偱娤嶡偡傞偑丄擃岥奧岥峯懁嵟忋抂偑峝岥奧偺崅偝傑偱嫇忋偟偰惓忢偲偡傞丅Blowing帪偺旲楻弌偱偼丄僗僩儘乕偱僐僢僾偺悈傪悂偒丄blowing帪偺屇婥旲楻弌偺桳柍偲掱搙傪旲懅嬀偱昡壙偡傞丅殝壓忈奞姵幰偱偼旲堲岮暵嵔婡擻偺掅壓偟偰偄傞応崌偑懡偔尒傜傟傞偺偱偙傟傜偺専嵏偺堄媊偼戝偒偄丅
師偵峔壒塣摦婡擻偱偼傑偢埨惷帪偺僠僃僢僋傪峴側偆丅岥怬偺埨惷帪偺忬懺傪尒偰傒傛偆丅幨恀俀偺傛偆偵嵍塃偳偪傜偐偵壓悅偟偰偄傞偙偲傕偁傞丅師偵愩偼埨惷帪丗姵懁偱堔弅偡傞偙偲傕偁傝丄岥峯撪偱偼寬懁偵曃埵偡傞偑丄塣摦帪乮撍弌帪乯偵偼幨恀俁偺傛偆偵姵懁偵曃埵偡傞丅師偵欩崌忬懺偱偼慜帟晹偺欩崌忬懺偲偟偰丄奐欩偺傒傪昡壙撪梕偲偡傞丅忋壓慜帟晹偺娫偐傜愩愲偑弌傞掱搙傪崌傢偣偰昡壙偡傞丅
師偵峔壒塣摦婡擻偺塣斖埻偱偼丄岥怬丄愩偺偦傟偧傟偺婍姱偺帺摦塣摦偺斖埻傪昡壙偡傞丅堦懁偵婡擻晄慡偑傒傜傟傞応崌偼姵懁偱昡壙偡傞丅忋壓岥怬偺愒怬偺忋壓墢傑偱払偡傞偐丄愩偑惓拞偐傜岥妏傑偱偺偳偺掱搙傑偱払偡傞偐丄愩偱杍晹傪墴偡嵺偺傆偔傜傒偺掱搙側偳傪昡壙偺婎弨偲偡傞丅師偵岎屳斀暅塣摦帪偵偍偗傞愩丄岥怬丄壓妠偺塣摦懍搙傪昡壙偡傞丅奺塣摦壽戣偺應掕帪娫偼3側偄偟俆昩娫掱搙偲偡傞丅傑偢丄塒帟傪偐傒偁傢偣偨忬懺偱俁昩娫偵壗夞奐暵偱偒傞偐傪傒傞丅岥怬偺婡擻偵娫戣偑偁傟偽儅峴僶峴僷峴偺壒偵榗傒側偳偑偱偰偔傞丅師偵壓妠偺奐暵塣摦傪俁昩娫偱壗夞偱偒傞偐傪幚巤偡傞丅壓妠偺挷愡偼峔壒偵廳梫側塭嬁傪媦傏偡丅傑偨塣摦偼丄嵍塃丄忋妠愗帟棤傪扏偔側偳偵偮偄偰傕僠僃僢僋偡傞丅愩偺塣摦偼幚嵺偺壒偯偔傝偺巇忋偘偺抜奒偵偁傞偺偱忈奞偑偁傟偽壒偺榗傒偑偱偰傢偐傝偵偔偄傕偺偵側傞丅埲忋娙扨側専嵏傪徯夘偟偨丅徻偟偔偼暥專3)傪嶲徠偝傟偨偄丅
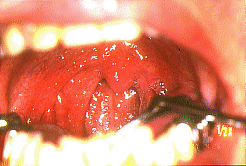 |
 |
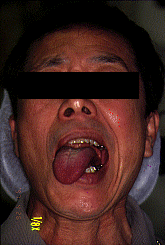 |
| 幨恀侾丂擃岥奧偺寬懁曃埵 丂丂丂丂丂乮僇乕僥儞挜岓乯 |
幨恀俀丂岥怬偺壓悅 丂丂丂丂丂乮塃懁偺旲怬峚偺徚幐乯 |
幨恀俁丂愩撍弌帪偺姵懁曃埵 |
嶲峫暥專
- 摗搰堦榊挊丗擼懖拞偺愛怘媺簭釆Q丄堛帟栻弌斉丄1993
- 愮栰捈堦曇挊丗擼懖拞姵幰偺婡擻昡壙丄僔儏僾儕儞僈乕丒僼僃傾儔乕僋丄1997
- 惣旜惓婸丗埉幃敪榖儊僇僯僘儉専嵏丄搶嫗丄僀儞僥儖僫弌斉丄1994
乥 傾僾儘乕僠(1) 乥 傾僾儘乕僠(2) 乥 傾僾儘乕僠(3) 乥 傾僾儘乕僠(4) 乥 傾僾儘乕僠(5) 乥